こんにちは、原 黒之介(はら くろのすけ)です。
サラリーマンの皆さまが「年収1,000万円 × 資産3,000万円」を実現するための情報を発信しています。
「退職まであと10年。資産形成、今からでも間に合うだろうか…?」
そんな不安を抱えながらも、
「まぁ、なんとかなるだろう」
「いざとなれば働けばいい」
「投資って難しいし、今さら始めても遅いよな」
と感じていないでしょうか?
実は、50代からでも投資による資産形成は十分可能です。
ただし、20代・30代とは異なり、
大きく増やすよりも、リスクを抑えながら“備える戦略”が重要になります。
本記事では、50代からでも安心して始められる投資戦略を5つ厳選してご紹介します。
「今からできること」に目を向けることで、将来の不安は必ず小さくなります。
50代からの投資で押さえておくべき前提
50代から投資を始めるなら、まず「現在のお金の状況」を整理することが大切です。
「現在のお金の状況」の整理
・月の収入と支出
・住宅ローンなどの固定費
・iDeCoやNISAなどの積立状況
・現在の貯金・投資資産のバランス
「え、iDeCoやNISAも投資なの?」と思った方へ
はい、iDeCoやNISAも“投資”に含まれます。
とくにNISAは株式や投資信託を使った運用が基本なので、「自分はまだ投資していない」と思っていた方も、実は投資を始めているケースが多いのです。
まずは全体を整理してみましょう(シミュレーション例)
仮に、以下のようなケースだとします:
■毎月の収支
月収 :50万円
支出 :18万円
住宅ローン :12万円
NISA積立 :5万円
月の残額 :15万円
■貯蓄
貯金 :200万円
投資資産(NISA等含む):300万円
ここで重要なのは、まず「生活防衛資金」を確保しておくことです。
生活費(18万)+住宅ローン(12万)=月30万円
→ これを12ヶ月分で360万円
この金額を現金で持っておくことで、何かあっても1年間は安心して生活できます。
さらに、教育資金や親の介護などの家族イベントが見えていれば、+αで備えておくとさらに安心です。
▸ 投資に使えるお金の見える化
生活防衛資金が確保できたら、次に「投資に回せる金額」を確認します。
この例では、
- 毎月の残り15万円
- NISAで積立中の5万円
→ 合計月20万円までが投資戦略の検討対象になります。
「そんなに余剰資金ないよ…」という方もご安心ください。
月1万円、3万円からでも、投資は十分にスタート可能です。
重要なのは、額の大きさではなく、無理のない範囲で“継続”できることです。
50歳からでもできる投資戦略5選
それでは、50歳からでも始められる投資戦略を5つご紹介します。
わたしも、この5つをやっています。
ポイントは、「節税+安定運用」を組み合わせることです。
1) iDeCo(イデコ)|節税しながらコツコツ増やす
iDeCoは、国が用意した“自分でつくる年金”です。
そして、毎月の積立額に合わせて所得税・住民税が軽くなる制度です。
口座の中で増えた利益にも税金がかかりません。
※年金で受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金で受け取る場合は「退職所得控除」が適用され、どちらも一定額までは非課税で受け取れます。
👍ここが良い
・掛金が丸ごと所得控除(税金計算の元から差し引かれる)
・利益も非課税で再投資できる
・口座管理がシンプル(自動で積み立て)
ただし注意点もあります。
- 原則60歳まで引き出せない(老後資金専用の貯金箱)
- 選ぶ商品しだいで値動きがある(リスクは小さめを選ぶ)
はじめ方(3ステップ)
①自分の掛金上限を確認(会社員・自営業などで異なる)
②証券会社を選ぶ(手数料が低い/商品が豊富なところ)
③低コストの投資信託を選んで毎月の金額を決める例:全世界株式(通称オルカン)/S&P500/バランス型
たとえば月1万円でもOK。税率にもよりますが、年に数万円単位の節税になる場合があります。
2) NISA(ニーサ)|自由度が高い“非課税の箱”を使い切る
NISAは、投資で出た利益や配当が非課税になる制度です。
iDeCoより引き出し自由度が高く、目的に合わせて使えます。
👍ここが良い
・いつでも売却・引き出しOK
・利益・配当が非課税で効率よく増やせる
注意点は、こちらです。
- 値動きのある商品を買うと元本割れの可能性はある
- 手数料の高い商品は避ける
はじめ方(3ステップ)
①生活防衛資金を除き、毎月いくら回せるか決める
②低コストのインデックス投信を中心に分散(オルカン/S&P500/バランス型)
③積立を自動化(“ほったらかし”で続けやすく)
iDeCoは“老後の金庫”、NISAは“使い勝手の良いポケット”。両輪で考えるとラクです。
3) 預貯金を増やす|“安心”は最強の投資
銀行預金・定期預金・個人向け国債など、元本が減りにくい資産で安全度を高める考え方です。
👍ここが良い
・いつでも使える安心感
・相場が悪い時の心理的な支えになる
注意点は、金利が低いので、増やす力(リターン)は小さいことです。
リスクは、無いですが、投資ではないので、ご注意ください。
はじめ方(3ステップ)
①生活防衛資金とは別に、短期目的資金(数年以内に使うお金)を預貯金で用意
②NISA・iDeCoの積立額とバランスをとる
③金利やペイオフの仕組みも軽くチェック ※一つの金融機関に1000万円以上預けない
旅行・車検・家電買い替えなど数年以内に使う予定がある分は、基本“預貯金側”に置くと安心です。
4) 余力が出たら高配当株|“配当”で楽しみながら続ける
配当(会社の利益の分配)を定期的に受け取れる株式やETFへの投資です。
👍ここが良い
・口座に現金が入ってくる実感がある
・NISAと組み合わせると配当も非課税で受け取れる
注意点もあります。
- 株価は上下する(一点集中はNG)
- 配当は将来も同じとは限らない(業績で変わる)
はじめ方(3ステップ)
①業種を分散(金融・通信・インフラ・消費など)
②1社あたりの比率を小さく(全体の5%目安など)
③「配当はボーナス」と考え、再投資か生活費の補助に回す
“狙い撃ちで一発逆転”はしない。 コツは“広く薄く長く”。
5) 半年に一度のリバランス|増え方・減り方の偏りを整える
増えすぎた資産クラスを少し売り、減ったところに回すことで、最初に決めた配分(例:株50%・債券50%)に戻す作業です。
リスク(上下のブレ)を一定に保ちやすく、高くなったものを売り、安くなったものを買う“自動の規律”になります。
やりすぎると手間やコストが増えるので半年〜年1回くらいで実施してみましょう。
はじめ方(3ステップ)
①自分の目標配分を決める(例:株60/債券40)
②半年ごとに現在の比率を確認
③5%以上ズレたら積立の配分や一部売買で調整
失敗しないための注意点とリスク管理
投資は「増やすこと」以上に、「減らさないこと」が大切です。
特に50代からは、時間をかけて取り戻す余裕が少なくなるため、リスク管理が重要になります。
ここでは、失敗を避けるために必ず押さえておきたい4つのポイントを紹介します。
1) 無理なリターンを追わない(詐欺に注意)
よくある失敗
- 「年利20%保証」などのうたい文句に惹かれて資金を失う
- 実態のない海外投資や仮想通貨案件に全額投入してしまう
理由
高すぎるリターンは、裏に大きなリスクが隠れている可能性が高いです。
投資の世界では、“ローリスク・ハイリターン”は存在しない、と覚えておきましょう。
対策
・公式な金融機関や証券会社経由で投資する
・年利は5%前後を現実的な目安にする
・契約書や説明資料を必ず読み、不明点は調べる
2) 短期トレードに手を出さない
よくある失敗
- 株やFXを数日〜数週間で売買し続けて損失が膨らむ
- ニュースや噂に振り回されて落ち着いた投資ができない
理由
短期売買は、経験や時間、集中力、そして迅速な判断が求められます。
プロでも毎回勝てるわけではなく、特に仕事や家庭と両立する人には不向きです。
対策
・積立投資など、長期を前提とした戦略を採用する
・「売る時期」を決めずに“ほったらかし”運用で時間を味方につける
3) リバランスの考え方
ポイント
リバランスは「資産の比率を元に戻す作業」です。
50代からは、資産の減少を防ぐ意味でも重要になります。
例
- 予定配分:株50%/債券50%
- 株価上昇で株が60%になった → 株を一部売って債券に回す
注意点は、頻繁にやりすぎると手数料や税金が増えます。
半年〜1年に1回にして始めてみましょう。
4) 周囲の意見より、自分のライフプランを優先
よくある罠
- 同僚や友人の「この銘柄が上がるらしい!」に流されてしまう
- 家族の反対で本来の計画を中途半端に変更してしまう
理由
人によって収入、家族構成、目的、リスク許容度はまったく違います。
他人の成功例が、自分にとって正解とは限りません。
対策
・投資の目的を「自分のライフプラン」に沿って設定する
・家族には投資方針を共有しておく(安心感にもつながる)
まとめ|50代からでも、未来の資産はつくれる
50代からの投資は、「遅いスタート」ではありません。
むしろ、これまでの経験や安定した収入を土台に、堅実に資産を守り増やせる時期です。
大切なのは、次の3つです。
★資産を守るポイント★
①生活防衛資金を確保する
②iDeCoやNISAなどの非課税制度を活用する
③無理のない金額で長期・分散投資を続ける
投資の世界では、「始めた日が一番若い日」と言われます。
今日から小さく始めれば、1年後、5年後、10年後には確実に差がつきます。
これからの10年を、不安から準備の期間に変えていきましょう。
未来の自分に「やっておいてよかった」と思えるよう、今日から一歩を踏み出してみてください。

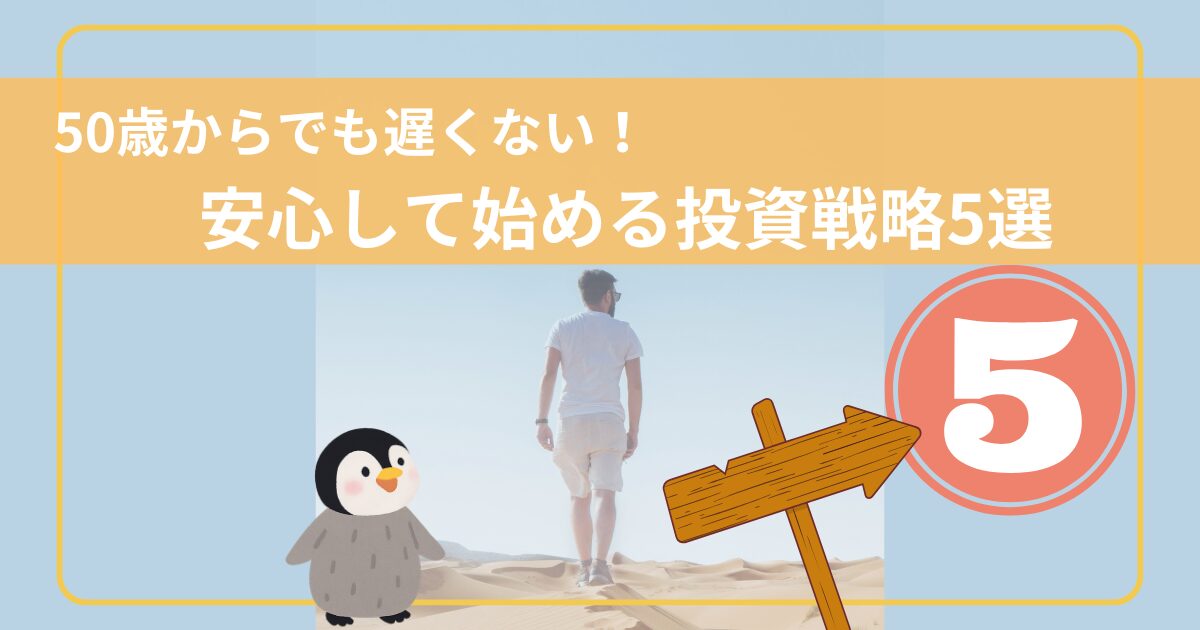
コメント