「iDeCoって、なんとなく聞いたことはあるけど、よくわからない…」
そんな方は、今すぐチェックしておくべき理由があります。
実は2025年から、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金上限額が大幅に引き上げられる制度改正が予定されており、制度の活用チャンスが拡大しています。
「NISAはやっているけど、iDeCoはまだ…」という方にこそ知ってほしい、税制優遇の大きなメリットです。
本記事では、iDeCoがどんな制度なのか、そして2025年の改正を前に今からできる3つの準備を、初心者にも分かりやすく解説します。
制度改正を味方につければ、将来の資産形成に大きな差がつくかもしれません。
ぜひ、このタイミングでしっかりチェックしておきましょう!
わたしのiDeCo体験談|仕方なく始めたけど“正解”だった話
わたしがiDeCoを始めたのは、転職がきっかけでした。
企業型確定拠出年金を辞める必要があり、「仕方なくiDeCoに移管した」というのが正直なところ。
当時は投資の知識もなく、「なんとなく、やらなきゃいけないから…」という感覚でした。
でも数年経った今、はっきりと言えるのは——
「あのとき、iDeCoを始めておいて本当に良かった」
ということ。
なぜなら、いつの間にか資産が増えていたからです。
節税され、運用益も非課税で、少しずつ確実に増えている。
これは「普通の貯金」では決して得られない実感でした。
わたしの過去のiDeCoは、こちらです。

そして今、2025年に向けて、iDeCoは制度改正の大きな波が来ています。
改正されてから始めるのではなく、今から始めておくことで、より制度を理解し、有利に活用できるのです。
今、iDeCoを始めるべき理由|制度改正前の“準備期間”が重要
「制度が変わるなら、改正されてから始めればいいのでは?」
そう思う方も多いかもしれません。
ですが、じつは「今」こそ、iDeCoを始める絶好のタイミングなのです。
その理由は、次の3つです。
理由①|制度改正の“恩恵”を受けるには、事前の準備がカギになる
2026年には、iDeCo制度の大幅な見直しが予定されています。
具体的には、以下のようなポイントが検討されています。
- 掛金の上限額の引き上げ
- 加入対象者の拡大
- 企業型DCとの併用条件の緩和 など
こうした改正により、これまで以上に柔軟で、誰でも使いやすい制度へ進化することが見込まれています。
しかし、制度が変わってから「さあ始めよう」としても、iDeCoは申し込みから運用開始までに1〜2ヶ月程度かかるため、改正のメリットを“即座に享受する”ことが難しいのです。
今から始めておけば、制度が変わったときにすぐに対応できる「準備が整った状態」にしておくことができます。
理由②|少額でも早く始めた人が有利になるのがiDeCoの特徴
iDeCoの最大の強みは、長期・積立・税制優遇。
この3つのメリットは、「できるだけ早く始めるほど効果が高まる」性質を持っています。
たとえば、同じ金額を毎月積み立てた場合、運用期間が長い人ほど複利効果が働き、結果的に大きな差が生まれるのです。
さらに、掛金は月5,000円からOKなので、「今は大きく積み立てられない」という人でも、少額からスタートしておくだけで、制度改正後にスムーズに増額することができます。
理由③|制度理解が深まり、改正後も“得する選択”ができる
iDeCoはNISAに比べて、やや制度が複雑です。
節税メリットや商品選びの自由度が高い一方で、「職業によって掛金の上限が違う」「原則60歳まで引き出せない」など、知っておきたい注意点も多くあります。
だからこそ、制度が変わる前から少しずつ慣れておくことが大切です。
たとえば、
- どんな商品が自分に合うのか
- 掛金の調整やスイッチングの方法
- 資産の増減に一喜一憂しない感覚
これらを「小さく始めて」経験しておくことで、制度改正後も落ち着いて有利な選択ができるようになります。
制度改正は“待つ”ものではなく“備える”ものだと思います。
そして、iDeCoの制度改正は、確かにビッグチャンスです。
ですが、その恩恵を最大限に活かすためには、制度が変わる前に動き出しておくことが重要です。
【ざっくり5分で理解】iDeCoのしくみとメリット
「iDeCoって結局どういう制度なの?」
「NISAと何が違うの?」
そう感じている方も多いと思います。
ここでは、専門用語ナシで、ざっくり5分で理解できるように、iDeCoの基本のしくみとメリットを紹介します。
◆ iDeCoとは?|自分でつくる“もうひとつの年金”
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、国が用意した“自分で年金をつくる”制度です。
60歳まで毎月コツコツと掛金を積み立てて、投資信託や定期預金などで運用していき、将来そのお金を年金または一時金として受け取ります。
ポイントは以下の3つ:
- 毎月の掛金額を自分で決められる(月5,000円〜)
- 商品も自分で選んで運用できる
- 原則60歳まで引き出せない=老後資金のための制度
◆ ここがスゴイ!iDeCoの3つの税制メリット
iDeCo最大の魅力は、節税効果の高さです。NISAよりも節税の幅が広く、長く使うほどメリットを実感しやすくなります。
① 掛金が全額「所得控除」に!
iDeCoに拠出した金額は、そのまま税金の計算から差し引かれます(所得控除)。
会社員やフリーランスの方は、住民税・所得税が年間数万円も軽くなることもあります。
例:
年収500万円の会社員が、毎月2万円(年間24万円)をiDeCoで積み立てると、
→ 年間約4.8万円の節税効果が見込めるケースも!
② 運用益が非課税に!
通常、株や投資信託で得た利益には約20%の税金がかかりますが、
iDeCo内の運用益はすべて非課税。利益をまるごと再投資できます。
③ 受け取り時も控除対象!
60歳以降にお金を受け取るときも、「退職所得控除」または「公的年金等控除」が使えます。
つまり、出すときも節税メリットを受けられるのです。
iDeCoはこんな人におすすめです。
| タイプ | 理由 |
|---|---|
| 将来に不安がある会社員 | 節税しながら老後資金を効率よく準備できる |
| NISAだけでは不安な人 | NISAと併用することで資産形成の軸が増える |
| 貯金がなかなか続かない人 | 強制的に毎月積み立て=“貯め癖”がつく |
| 節税メリットを最大限使いたい人 | 年末調整・確定申告で控除が受けられる |
ただし、注意点もあります。
①60歳まで原則引き出せない
→ 途中で使うことはできないので、「生活資金」とは切り分けましょう。
②掛金の上限は人によって違う
→ 会社員、自営業、公務員などで月の上限額が異なります。
③商品選びや証券会社選びが重要
→ 手数料や商品ラインナップは証券会社ごとに異なります。
iDeCoは、「老後のお金を少しでも安心して備えたい」という方にとって、非常に有利な制度です。
特に、税制の優遇を活かしながら、長期で積み立てるというスタイルは、これからの時代に合った“守りの資産形成”とも言えます。
次の章では、よく比較される「NISAとの違い」について、具体的に見ていきましょう。
iDeCoとNISAの違いとは?|目的・使い方の住み分け
iDeCoとNISAは、どちらも「資産形成に使える“税制優遇制度”」です。
「どっちを先に始めたらいいの?」「どう使い分ければいいの?」
そんな疑問を持っている方も多いと思います。
この章では、2つの制度の違いと、それぞれの目的に合った活用法をわかりやすく解説します。
◆ iDeCoとNISA、ざっくり比較表
| 比較項目 | iDeCo(イデコ) | NISA(ニーサ) |
|---|---|---|
| 主な目的 | 老後資金の形成(60歳まで引き出せない) | 資産形成(目的や期間に縛りなし) |
| 掛金(投資額) | 月5,000円~/上限あり(職業で異なる) | 年間120万円〜360万円(新NISA枠) |
| 税制優遇 | 掛金が所得控除、運用益非課税、受け取り時も控除 | 運用益が非課税 |
| 引き出し可能時期 | 原則60歳まで引き出せない | いつでも引き出し可能 |
| 対象商品 | 投資信託・定期預金・保険など | 株式・投資信託・ETFなど |
| 向いている人 | 長期でコツコツ、老後に備えたい人 | 中長期で柔軟に運用したい人 |
◆ 目的が違うから「併用」が正解!
iDeCoとNISAは競合する制度ではなく、むしろ補完し合う制度です。
- iDeCoは「老後の安心のため」
→ 引き出し制限があるぶん、確実に貯めることができ、税制優遇も手厚い。 - NISAは「将来の選択肢を増やすため」
→ 教育費やマイホーム、転職など、ライフイベントに備えて柔軟に活用できます。
つまり、iDeCoは“守り”、NISAは“攻め”の資産形成ともいえるでしょう。
◆ どっちから始めればいいの?
これには明確な正解はありませんが、以下のような考え方が参考になります:
▶ 生活に余裕があり、節税を重視したい人
→ iDeCoからのスタートがおすすめ
理由:所得控除による節税効果がすぐに実感できるため
▶ 万が一のためにいつでも引き出せる資金をつくりたい人
→ NISAからスタートが安心
理由:生活防衛資金や中期的な資金に使いやすい
▶ 本気で資産形成に取り組みたい人
→ 両方を併用するのが最適解
理由:それぞれのメリットを最大限活かせる
◆ わたしのケース|iDeCo→NISAの順で始めた理由
わたし自身は、転職時の企業型DCの移管をきっかけにiDeCoから始めました。
当時は「節税になるらしい」となんとなく続けていましたが、あとからNISAにも興味を持ち、併用を始めました。
結果的に、「60歳以降の資産はiDeCo、柔軟に使いたい資産はNISA」という使い分けができ、資産の目的がはっきりして安心感が増しました。
◆ まとめ|どちらかではなく、「目的」で使い分けよう
iDeCoもNISAも、それぞれに強みがあり、ライフスタイルや目標によって最適な使い方が異なります。
大切なのは、「なんとなく」ではなく「何のために使うか」を意識すること。
制度の仕組みを理解したうえで、自分に合った順番でスタートしてみてください。
次の章では、いよいよ実践編。
初心者がiDeCoを始めるための3ステップを、わかりやすくご紹介します。
初心者でも安心!iDeCoを始める3ステップ
「iDeCoの仕組みはわかったけど、実際どうやって始めればいいの?」
そう思っている方のために、ここでは初心者でも迷わずスタートできる3ステップを紹介します。
実は、iDeCoはたった3つの手順を踏めば誰でも簡単に始められます。
書類が多そう…手続きが面倒そう…というイメージを払拭して、一緒に一歩踏み出してみましょう。
STEP 1:自分の「加入資格」と「掛金の上限額」を確認しよう
iDeCoは、職業や年金の加入状況によって毎月積み立てられる上限額が異なります。
まずは、自分がどの区分に当てはまるかを確認しましょう。
| 区分 | 掛金上限(月額) | 備考 |
|---|---|---|
| 自営業・フリーランス | 68,000円 | 国民年金のみの人 |
| 会社員(企業年金なし) | 23,000円 | 中小企業など |
| 会社員(企業型DCあり) | 20,000円 or 12,000円 | 加入状況によって変動 |
| 公務員・教職員 | 12,000円 | 共済年金加入者 |
| 専業主婦・主夫 | 23,000円 | 配偶者の扶養に入っている場合 |
👉総務や人事部に「企業型年金に加入しているかどうか」を聞くと確実です。
STEP 2:証券会社を選んで申し込もう(手数料に注目!)
iDeCoの申し込みは、証券会社や銀行などの運営管理機関を通じて行います。
会社によって、手数料・商品ラインナップ・サポート体制が異なるため、自分に合った金融機関を選びましょう。
▶ 人気の金融機関例(2025年現在):
| 証券会社 | 特徴 |
|---|---|
| SBI証券 | 手数料が業界最安水準。商品数が豊富で人気No.1 |
| 楽天証券 | 楽天ポイントが貯まる。初心者にも使いやすい |
| 松井証券 | サポートが丁寧。初心者向けサービスが充実 |
※申し込みから実際に積立が始まるまでに1~2ヶ月程度かかるのが一般的です。早めに申し込みましょう。
ちなみに、わたしは、SBI証券を利用しています。
STEP 3:商品を選んで積み立てを開始しよう
証券会社の申し込みが完了したら、いよいよ「運用商品」を選んで積み立てをスタートします。
▶ 商品の種類(代表例):
| 商品タイプ | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 投資信託(株式型) | 値動きは大きいが長期で成長が期待 | 増やしたい人、長期運用向き |
| 投資信託(債券型) | 安定性重視。リスクを抑えたい人向け | 値動きが気になる人 |
| 定期預金 | 元本保証。利率は低め | 元本割れが不安な人、初心者向け |
👉最初は「バランス型」など複数に分散投資されている商品を選ぶと安心です。
◆ 補足:困ったときはサポートを活用しよう
証券会社には、iDeCo専用のコールセンターやチャットサポートがあります。
迷ったときは遠慮なくプロに相談しましょう。「とりあえず資料請求だけ」でもOKです。
◆ まとめ|始めるハードルは、思っているよりずっと低い
iDeCoは、「投資初心者には難しそう」と思われがちですが、実は仕組みを理解すればとてもシンプルです。
- 自分の掛金上限を確認
- 証券会社を選んで申し込む
- 商品を選んで積み立て開始
この3ステップだけで、あなたの老後資産づくりが今日からスタートできます。
まとめ|“いつか”じゃなく“今から”で、未来の自分を助ける
iDeCoは、税制優遇を受けながら将来に備えられるお得な制度です。
しかも、月5,000円から始められ、長く続けるほど効果が高まります。
わたし自身、義務的に始めたiDeCoが、今では「やっておいてよかった」と思える存在になっています。
数年後に資産が増えていたときの安心感は、思った以上に大きいものでした。
制度改正はチャンス。でも準備は今からです!
2025年からの制度改正で、iDeCoはさらに使いやすくなります。
でも、始めるには申し込みや書類の準備が必要なので、今から動いておくことで改正の波にしっかり乗れます。
迷ったら、小さく始めてみるのがコツ
いきなり全額積み立てる必要はありません。
まずは資料請求だけでもOK。少額からでも始めてみることで、制度の理解も深まり、将来の自信につながります。
「やっておけばよかった」より、「やっててよかった」へ。
未来の自分のために、今日から一歩踏み出してみましょう。

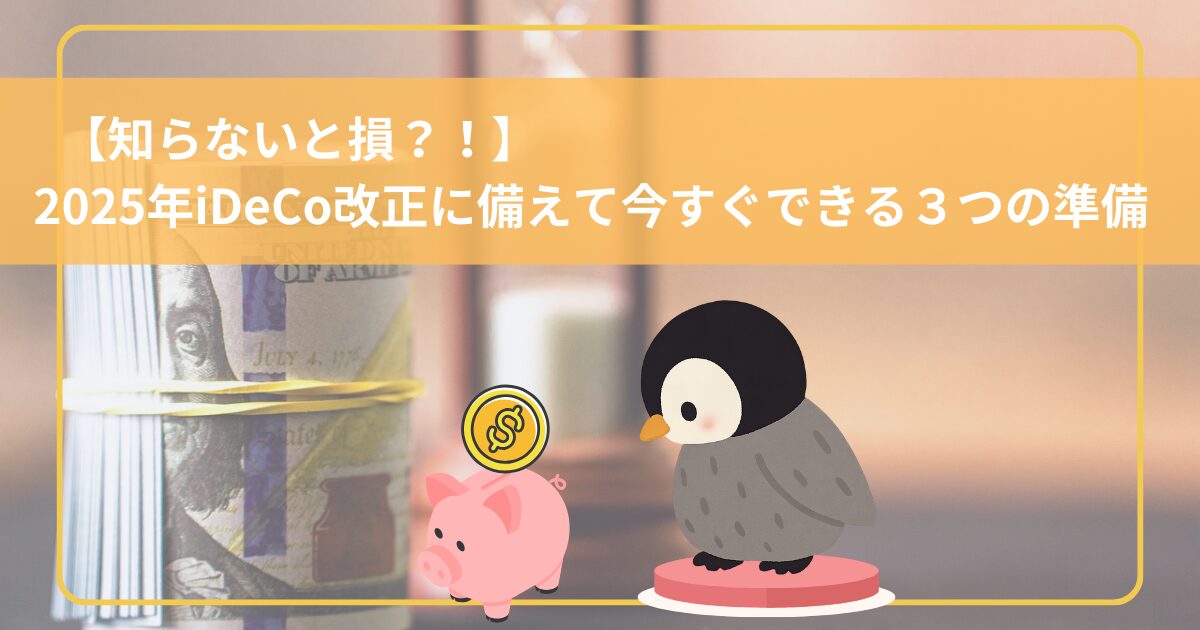
コメント