 はらぐろ
はらぐろこんにちは、はらぐろです。
今回は、「投資を始めたいけど、なんだか怖い」「相場が不安定で、今始めるのは損なんじゃない?」と悩んでいる方向けに、投資を始めるタイミングや不安定な相場を乗り切るコツをお伝えしたいと思います。
わたし自身、サラリーマンとして仕事をしながら投資をしてきて、リーマンショックやコロナショックなどの大きな下落局面も経験してきました。正直、値動きを見ると心がザワザワしますが(笑)、長期でコツコツ続けることでしっかりリターンを得られ、資産を着実に増やしてきました。
投資を始めるタイミング
最近、トランプ関税のニュースが頻繁に取り上げられています。
世界的な政治・経済の影響で株価が下落する場面も増え、投資をしている人たちはヒヤヒヤしているかもしれません。わたしも保有している銘柄や投資信託の価格が日々変動するので、あまり見ないようにしています(笑)。
昨年、新NISA(少額投資非課税制度)もスタートし、「そろそろ投資を始めてみようかな」と考える方が増えています。
一方で、こういう不安定な時期に投資を始めるのは勇気が要りますよね。
「下落相場の真っ最中に買うのは怖い」「もっと安定したタイミングで始めたい」と思う方も多いと思います。
しかし、個人的には、「投資を始めるベストタイミングはいつでも良い」と考えています。
理由はシンプルで、「タイミングの見極め」よりも「どれだけ長く投資を継続できるか」の方が、成果につながりやすいからです。
市場の動きを完璧に予想するのは、プロでも至難の業です。
時々「○月は暴落が来る」といった話題が出ても、実際は当たることもあればハズレることもある。だったら、相場の上下をうまく読もうとするよりも、「時間」を味方につけて、コツコツと投資を積み重ねる方が現実的にリターンを得やすいのです。
もし始める時期を先延ばしにすると、複利効果が働く期間が短くなります。
複利効果とは「得られた利益を再投資して、雪だるま式に資産を増やす」考え方で、投資期間が長いほど恩恵が大きいのが特徴です。
逆に、多少高値で買ってしまったとしても、長期的には成長や回復が期待できることが多いので、結果的にプラスになる可能性が高いとも言われています。
こうした理由から、**「いつか始めよう」ではなく、「今から始めて、なるべく長く続ける」**ほうが、結果的にいいタイミングで投資できるケースが多いというわけです。
実際、わたしもリーマンショックやコロナショックを経験しながらもコツコツ買い増しを続けたことで、結果的に大きく資産を伸ばすことができました。
分散投資とは何か
次に、「分散投資」の考え方についてお話しします。
分散投資とは、その名のとおり、投資先を複数に分けてリスクを抑える戦略です
。わたしも投資を始めたばかりの頃は「ひとつの銘柄で大きく儲けたい!」と思っていましたが、これはかなりリスキーなやり方です。
株式ひとつに全力投資して大当たりすればラッキーですが、外れれば大損失を被るかもしれません。
そこで登場するのが以下のような分散投資の方法です。
★分散投資の方法★
1.株式(国内・海外)
2.債券(国債・社債)
3.投資信託やETF(複数銘柄をまとめた商品)
4.不動産
5.コモディティ(貴金属・エネルギーなど)
それぞれ値動きのパターンやリスク・リターンが異なるので、一部が下落しても、他の資産が上昇すれば損失を補う可能性が高まります。
特に投資信託やETFは、「少額から複数銘柄に投資できる」点が魅力です。
分散投資をやりやすく、初心者にも取り組みやすいのが特徴といえます。
分散投資のメリットは「リスクを分散する」だけでなく、「メンテナンスをしやすい」点にもあります。複数の資産クラス(株や債券など)に資金を割り振っておけば、どれか一つが大きく下落したときも全体のバランスを取りやすいからです。
ある程度、投資の経験を積んだら、「どの資産にどれくらい配分するか」を年に1回程度見直す「リバランス」を意識すると、より安定感のあるポートフォリオが作れます。
長期投資のメリット
短期売買を繰り返していると、小さな値動きを追いかけることになるので心理的ストレスが溜まりやすいです。
わたしも最初はデイトレード的なことに興味を持ちましたが、仕事との両立も大変で、結局は長期投資メインに切り替えました。
そのほうが結果的にメリットが大きいと感じたからです。ここでは、長期投資における代表的なメリットを3つ紹介します。
1. 一時的な下落リスクへの対抗
政治的な問題や景気サイクルの変化などで、短期間に株価が大きく動くことは珍しくありません。
しかし、経済全体を長期的に見ると、ゆるやかに成長してきた歴史があります。
そのため、一時的に急落しても、長い目で見れば回復するケースが多いんです。
リーマンショックのときは世界的に大暴落でしたが、その後の回復局面でプラスに転じるケースが大半でした。
2. 複利効果の恩恵
投資で得られたリターンを再投資すると、資産は複利的に増加していきます。
雪だるまを転がすように、投資額が少しずつ大きくなり、それに伴って利益も増えやすくなるイメージです。
この複利効果を最大限に活かすには「時間」が必要なので、早めに投資を始めて長く続けるのがベストなのです。
3. 心理的負担の軽減
短期売買だと、ちょっとした値動きに敏感になってしまいます。
仕事中もスマホで株価をチェックして一喜一憂したり、急落すると夜眠れなくなったり…。
しかし、「10年、20年先を見据えた投資」というスタンスなら、目先の上げ下げにあまり振り回されません。
これは本業を持つサラリーマンにとっては大きなメリットです。
投資だけに時間を割けない状況でも、余裕を持って運用を続けられます。
不安定な時期にも投資を続けるには
相場が不安定になると「今は一旦やめようかな」と思うかもしれませんが、投資は続けることに大きな意味があります。
わたしはリーマンショックやコロナショックのときも投資を継続し、むしろ下落時に買い増しをすることで大きな恩恵を受けられました。
ここでは、不安定な時期でも投資を続けるための3つのポイントを紹介します。
定期買付(ドルコスト平均法)を利用する
相場が上がっているときも下がっているときも、一定額ずつ定期的に投資を行う「ドルコスト平均法」を利用すると、購入価格が平均化されます。
高値掴みのリスクを減らせるだけでなく、下落時にもしっかり買うことで、回復局面でのリターンを大きく得られます。
特にサラリーマンの方は毎月の給料日などに合わせて自動積立する仕組みを作ると、手間もかからず継続しやすいです。
投資計画の見直しとメンテナンス
長期投資が基本方針でも、年に1~2回はポートフォリオを確認しましょう。どのくらいのリスクを取るか、どの資産にどれだけ配分するかなど、当初設定した目標やリスク許容度と照らし合わせて、大きくズレていないかをチェックします。
必要に応じてリバランスを行うことで、「株式が増えすぎたから一部を債券に回す」「特定の投資信託が過剰に比率を占めているから別のファンドと組み替える」といった調整ができます。
これによって、急激な相場変動が起こったときもリスクをコントロールしやすくなります。
十分な余剰資金で行う
これが意外と重要です。生活資金や緊急時に必要な資金まで投資に回してしまうと、相場が不安定になったとき「資金が足りないから仕方なく損切り…」という事態に陥りがちです。
余裕資金で投資を行うことで、たとえ一時的に含み損が出ても慌てずにホールド(保有)でき、回復を待つ余裕が生まれます。
わたしも投資を始めたばかりのときは、ちょっと無理してしまい、急な出費に対応できず焦った経験があります。
そんな失敗を防ぐためにも、まずは貯蓄を確保し、それとは別に投資資金を確保することをおすすめします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は、投資を始めるベストタイミングと、不安定な相場でも乗り切るためのポイントを紹介しました。
サラリーマンとして毎日働きながら、資産を増やしていくうえで大切なのは、「焦らずに長期でコツコツやる」ということに尽きます。わたしがリーマンショックやコロナショックの混乱期を経験して思ったのは、「相場はいつだって不安定要素を抱えているけれど、長期的には成長している」ということ。
だからこそ、基礎的な知識を身につけて、ブレずに続ける姿勢が大切です。
- タイミングよりも大切なのは投資期間の長さ
- 分散投資でリスクを軽減しつつ運用する
- 複利効果を活かし、心理的負担も抑えられる長期投資がおすすめ
- 不安定な時期ほど「ドルコスト平均法」や「リバランス」を活用
- 余剰資金を使うことで、急な出費や暴落にも耐えやすい
特に30代~50代のサラリーマンの方は、投資で得た利益を再投資しながら老後資金を作ったり、あるいはセミリタイアを目指したり、いろいろな選択肢が見えてくる時期だと思います。
投資を通じてお金の不安を少しでも減らし、余裕を持って自己成長やキャリアアップに集中できたら最高ですよね。
もちろん、投資にはリスクもあります。
だからこそ「無理せず長期目線で続けられる仕組み」を持つことが大事です。もしまだ投資を始めていない方は、NISAやiDeCoといった優遇制度を活用しながら、余剰資金で少額から始めてみてはいかがでしょうか。
これからの不安定な時期も、しっかり投資を続けて資産形成を進めていきましょう。

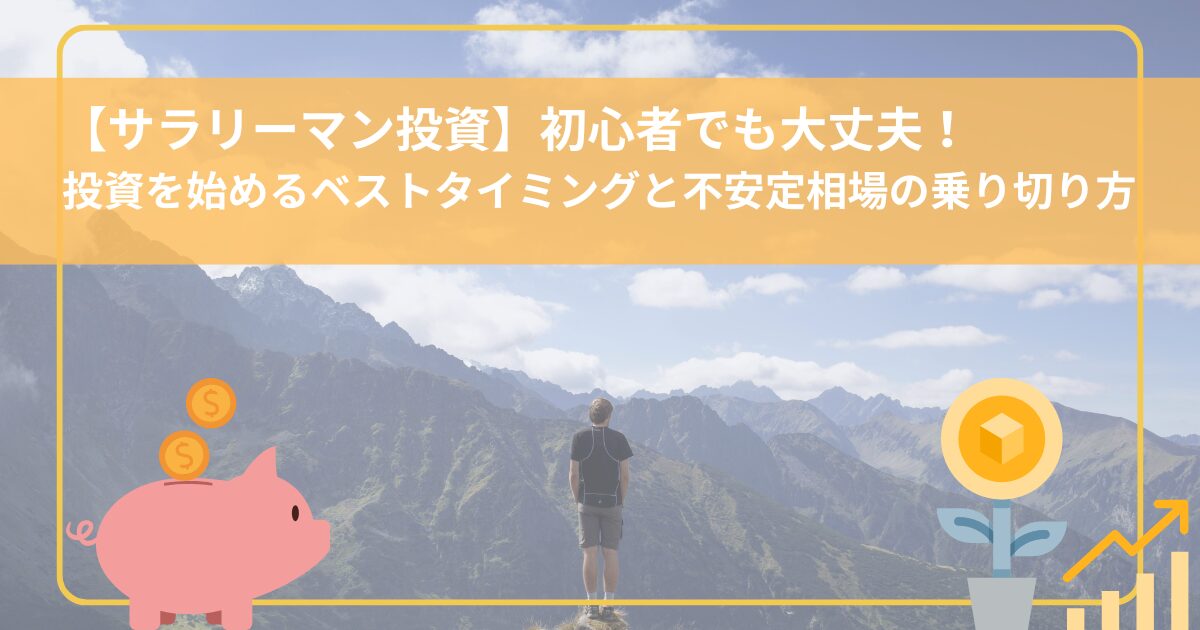
コメント