 はらぐろ
はらぐろこんにちは、はらぐろです。
今回は、月に一冊の読書の3月のおすすめを紹介します!
マーケティング関連の本を読もうと思い、YouTubeでも紹介されている細田高広さん著『コンセプトの教科書 あたらしい価値のつくりかた』です。
マーケティングにかかわっている方だけではなく、多くのビジネスマンに読んでいただきたい本でした!
なぜこの本を読んだか
2025年の目標の一つが、月に一冊の読書です。
そこで、3月はマーケティング関連の本を読もうと思い、『コンセプトの教科書 あたらしい価値のつくりかた』を読みました。
前回に引き続き、マーケティング関連の書籍です!
実は、今年に入ってから「新規事業の立ち上げ」と「イベント出展」を企画していて、コンセプトを決める段階で悩んでいました。
いくつかYouTubeを検索して動画を見ていまして、細田高広さんの動画が面白く、この本だ!と思い、さっそくアマゾンでぽちりました。
これが今年4冊目のビジネス書になります。
結論から言うと、今までにない教科書的なアプローチで「コンセプトづくり」のプロセスが丁寧に解説されていて、とても面白かったです。
読みやすかったし、実践に移しやすい内容だったので、あっという間に読み終わりました。
マーケティング初心者のわたしでも、すんなりと理解できるように工夫されているのが本書の魅力だと思います。
本のポイント
わたしなりに、この本のポイントを整理しました。大きく3つに分けて紹介します。
①コンセプトとはなにか
第一章の冒頭では、「ビジネスにおけるコンセプト」の定義が明確に示されています。
それによると、コンセプトは「価値の設計図」であると書かれていて、わたしとしてはすごくしっくりきました。
さらに、「コンセプトはキャッチコピーではない」「コンセプトはアイディアではない」「コンセプトはテーマではない」という記述もあり、これまで自分が思っていた「なんとなくのコンセプト」は、実は全然コンセプトじゃなかったんだなと気づかされました。
たとえば、わたしがこれまで企画していたイベントの“コンセプト”と呼んでいたものは、実質キャッチコピーだったり、単なるアイディアの羅列だったり…。
ちょっと恥ずかしいんですが、思い当たるフシが多すぎて苦笑いしてしまいましたね。
でも、そういう気づきを得られたのは大きいです。まずはここから改善していこうと思いました。
②コンセプトの作り方
本書で特に参考になったのが、コンセプトを導くための「問い」のつくり方を詳しく解説してくれている点です。
「問い」がなければ、作りたい価値や設定したいゴールが明確にならないので、そもそもコンセプト自体がブレブレになってしまうということがよくわかりました。
ただ、実際に自分でやってみると意外と難しくて、「顧客が本当に求めているものは?」「イベントで得られる体験価値は?」といった問いをしっかり言語化するのは、慣れが必要だと痛感しています。
このパートは読みごたえがあって、理論の説明だけでなく、具体的に何をどう考えればよいかが書かれているので、「なるほど」と納得できる部分が多かったです。
でも実際、手を動かしてみると思いのほか苦戦しているので、繰り返し練習して自分の血肉にしていく必要があるなと思いました。
③重要なストーリー
本書の後半で強調されているのが、「コンセプトにはストーリーが欠かせない」という点です。前半から具体例として「スターバックス」の事例が紹介されているので、誰もがイメージしやすいのが良いところ。
スタバが大事にしているストーリーや世界観が、いかに消費者の行動や体験を支えているかを改めて知ることができました。
わたしも普段スタバをよく利用しますが、こうして改めて読み解いてみると、「なるほど、だからスタバは強いのか…」と納得させられる部分が多かったですね。
単に「おしゃれなカフェ」というだけではなく、そこで過ごす体験や雰囲気そのものを大切にしている。
そういった背景にあるコンセプトやストーリーの設計が巧みだからこそ、多くのファンを獲得し続けているんだなと感心しました。
参考になったこと
わたしが本書を読んで一番参考になったのは、「作り方の手順」に明確なガイドがあったことです。これまで何となく感覚に頼って、思いついたアイディアを関係者にレビューして…という流れで、結果オーライを狙うスタイルでした。でもそれだと、チーム内で意見が割れたときに、どこがズレているのかをはっきり言語化できなかったんですよね。
この本の提案するステップを踏めば、少なくとも自分たちが何を目指していて、その価値を誰に提供したいのかが言葉で整理しやすくなると感じました。
「コンセプトは価値の設計図」という言葉にもある通り、そもそも設計図が存在しないのに、家(=プロジェクトや企画)を建てようとしていた…なんてことに思い至り、目からウロコでした。
特に、著者が繰り返し強調している「顧客視点の重要性」は、最近のマーケティング本でよく言われることですが、この本は「具体的にどうやってお客様のインサイトを見つけるか」という流れも丁寧に解説してくれているので、すごく現実的なんです。
さらに、ストーリー化が欠かせない理由をスタバの例で納得させてくれるので、一連のプロセスが筋道立ってわかりやすかったですね。
実践すること
この本を読んで、「これは使える!」と思ったことはすぐに実践するようにしています。前回読んだマーケティング本の内容も加味しつつ、以下の3つを意識して進めてみました。
- 顧客視点で作る
まずは、今回の新規事業とイベントのターゲットとなる顧客をもっと掘り下げることから始めました。年齢や属性だけでなく、「その人がどんな課題を抱えているのか」「どんな経験を求めているのか」を具体的に洗い出しています。単なる思い込みや常識に捉われないように、できるだけリサーチや実際の声を集めるようにしているところです。 - インサイトを意識する
顧客が口にしない本音や、潜在的な欲求を意識してみることにしました。簡単に言うと「顧客のホンネは何なのか?」という部分です。そこに気づくためには、やはり普段から観察とヒアリングが重要だと痛感しています。イベントの企画でも、ただ「面白そうだから」「集客できそうだから」という理由だけで決めるのではなく、「誰に、どんな体験をしてもらい、どんな価値を提供するか」という視点を常に忘れないように心がけています。 - ストーリーにする
最後に、わたしが一番意識するようになったのは「ストーリー化」です。今回のイベントでも「この企画を通して参加者にどんな物語を味わってもらうか」を考え始めました。たとえば、イベントの冒頭から終了後まで、お客様の行動と気持ちの変化を「ストーリー」として描くんです。これはまだ始めたばかりで、正直言うと慣れない部分も多いんですが、関係者への説明が以前よりうまくいくようになった気がします。
こうしてコンセプトを明確にして、関係者にレビューしたところ、「具体的にイメージしやすいね」と言ってもらえることが増えました。
まだブラッシュアップする余地はたくさんありますが、確実に手ごたえを感じています。
イベントまで時間はあるので、何度も修正を繰り返して完成度を高めていきたいですね。
まとめ
今回ご紹介した『コンセプトの教科書 あたらしい価値のつくりかた』は、わたしのようにマーケティングを勉強している方や、新規事業を企画している方だけでなく、普段の業務で「どうやって価値を作り出せばいいんだろう?」と悩んでいる多くのビジネスマンに読んでいただきたい本だと感じました。
30代~50代のサラリーマンが、これからさらにキャリアアップを目指していくうえで、何か新しいアイディアを打ち出すときやプロジェクトを進めるとき、「コンセプト」という土台を固めるスキルは必ず役立つはずです。
この本は、実践例や具体的なワークを交えながら、コンセプトづくりの大切さと、その手順を分かりやすく教えてくれます。
わたし自身、イベントの企画を通して改めてその有用性を体感しているところです。
感覚に頼らず、「価値の設計図」を描いてからアクションを起こすだけで、プロジェクトに説得力が増すのを実感しています。
もしあなたが「いまいちピンとくるコンセプトが作れない」「アイディアはあるけど形にならない」と感じているなら、この本が大きなヒントになるはずです。
ぜひ一度、じっくり読んでみてください。きっとビジネスの現場で役立つ考え方が身につくと思います。わたしもまだまだ修行中ですが、一緒に成長していきましょう。
それでは、次回の本の紹介もお楽しみに!実践しながら学ぶ姿勢を大切にしつつ、皆さんに役立つ情報を届けられるようがんばっていきます。
次はどんな本やノウハウに出会えるのか、わたし自身も楽しみです。お互いスキルアップを目指して、これからも進化していきましょう!

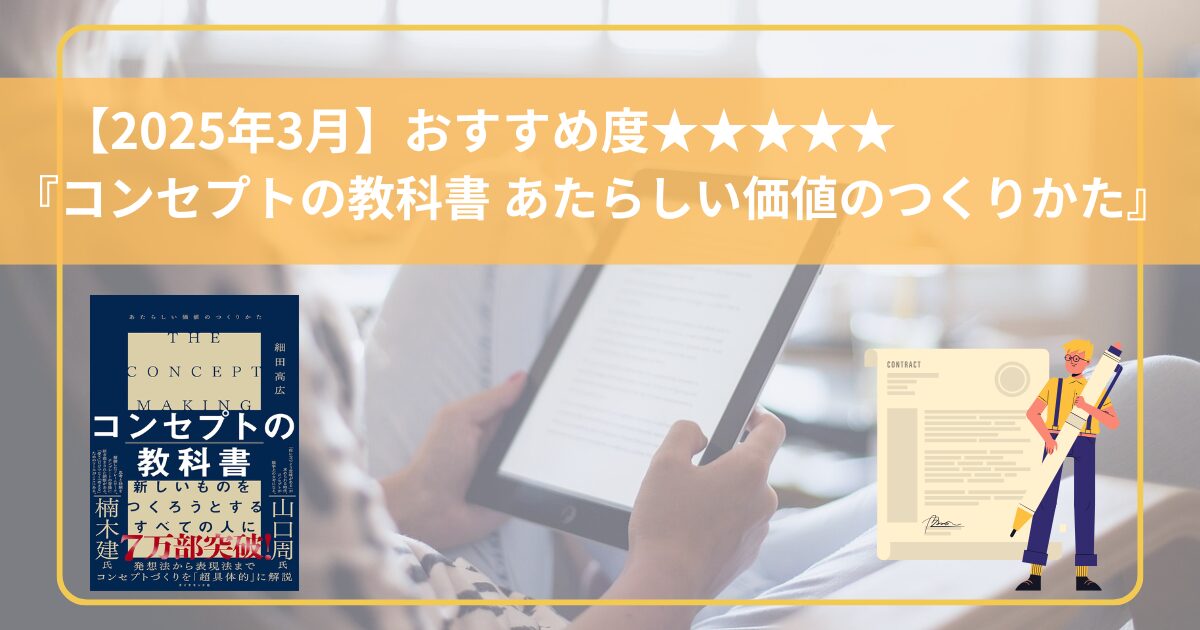
コメント