 はらぐろ
はらぐろこんにちは、はらぐろです。
最近、ニュースを見ていると「米国の景気が悪化しそうだ」「日米の株価が大幅に下落した」といった話題を耳にする機会が増えてきましたよね。
特にトランプ政権の話題がまだまだ尽きず、為替も株価も不安定な動きをしていると感じる方も多いのではないでしょうか。
こういった不安定な相場でも、サラリーマンだからこそ実践しやすい「長期投資スタイル」を紹介したいと思います!
相場の上下に不安を感じる理由
最近のニュースは、米国政権の動向や、世界経済の先行き不透明感が大きく取り上げられていますよね。
その影響を受けて、日米株価や為替相場も上下を繰り返し、何となく落ち着かない雰囲気があります。
わたしも資産が増えてきたぶん、どうしても変動幅が大きくなりがちで、下落相場になると気が気じゃありません。。。
こちらが、2025年3月23日のSBI証券分のわたしの資産です。
半年を見てみると、けっこう変動ありますよね。。


ピークの資産残高は、27,998,334円です。
もっとも下落したタイミングが、25,660,717円
差は、-2,337,617円で、約8.3%の下落になります。
実際に「大丈夫かな…」と不安になることもしばしばです(苦笑)
そもそも、景気のニュースに左右されやすい心理には、どんな背景があるのでしょうか。
一つ言えるのは、人間はもともと「損失回避バイアス」を強く持っている、という点です。
損をするかもしれないと思うだけで、不安が膨らんでしまうわけですね。
特に投資の場合は、日々の値動きが可視化されているため、「今日は◯万円下がった」「また株価が下がってる」といった情報に簡単にアクセスできてしまいます。
また、人は「短期的な価格変動」に目が行きがちという側面もあります。
ニュースサイトやSNS、テレビの速報などで、「今日の株価は前日比マイナス○%」と流れれば、それだけで慌ててしまいますよね。
どうしても大きく値下がりした瞬間だけ報道が加熱するので、さらに不安が増長されるのです。
情報自体が瞬時に入手できる現代だからこそ、短期的な乱高下に翻弄(ほんろう)されやすい心理状態になると考えられます。
短期投資と長期投資の違い
投資には大きく分けると「短期投資」と「長期投資」があります。
iDeCoやNISAは、基本的には長期投資の枠組みに位置づけられますが、中にはNISAで短期的な利益を狙おうとする人もいるかもしれません。
まずは、この両者の違いについて簡単に整理してみましょう。
短期投資
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 相場が急上昇したときに大きなリターンを素早く獲得できる可能性がある 相場の変化に応じて売買を頻繁に行うため、大きく稼げるタイミングを逃しにくい | 相場を常にチェックする必要があるため、本業と両立しにくい 売買手数料や税金など、コストがかさみやすい 予想外の下落に対して、精神的負担が大きい |
長期投資
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 毎日の値動きに振り回されにくく、精神的に安定しやすい 複利効果(資産が雪だるま式に増えていく効果)を狙いやすい 株価が一時的に下落しても、長期的な上昇トレンドに乗れば回復が期待できる | すぐに大きな利益を得るのは難しい 資金がある程度長期間ロックされるため、急にまとまったお金が必要になった場合に対処しにくい 企業や経済の成長を長期で見極める必要がある |
短期投資は、大きく儲けるチャンスがある一方で、サラリーマンのように日中は仕事をしている方にとっては、値動きをチェックし続けるのは至難の業ですよね。
頻繁に相場をチェックできないと、タイミングを逃してしまいがちですし、心理的にも負担が大きいでしょう。
一方、長期投資であれば、日々の細かい値動きにはそこまで神経質になる必要がありません。
もちろん経済状況を全くチェックしないわけにはいきませんが、「上がったり下がったりを繰り返して、最終的に右肩上がりになる」という資本主義社会の歴史を前提に、腰を据えた投資が可能になるのです。
サラリーマンであれば、仕事のスキルアップや給与アップも目指しながら、無理なく投資を続けられるメリットがありますよね!
サラリーマンが長期投資を選ぶメリット
では、なぜサラリーマンには長期投資が向いているのでしょうか。
以下のポイントがあると思います。
安定収入がもたらす投資の継続性
サラリーマンの最大の強みは、毎月安定した給与収入を得られることです。
投資の王道は「時間を味方につける」ことなので、コツコツ積み立てていくのが非常に有効です。
投資資金を定期的に投入し続けることで、「高い時も買うし、安い時も買う」を繰り返し、取得単価を平準化できます。
景気が悪化するかも…と感じるタイミングでも、続けることで長い目で見ればリスクが分散され、資産が増えやすくなるでしょう。


本業との両立を図るポイント
長期投資であれば、日々の売買タイミングを必死に追う必要がありません。
どうしても仕事に集中すべき時期や繁忙期などは、相場をチェックする余裕がなくなりますよね。
もし短期投資を選んでいたら、残業続きのときに「株価が暴落している…どうしよう」と慌ててしまい、仕事にも影響が出てしまうかもしれません。
その点、長期投資であれば「今は焦らず、そのまま積立と保有を継続しよう」と割り切れるので、精神面の負担が少ないです。


さらに、サラリーマンは給与収入に加えて、昇給やボーナスなどのタイミングで投資に回す資金を増やすこともできます。
つまり、本業で収入アップを目指しながら、投資も同時進行できるというわけです。
短期投資のように張りつく必要はありませんし、投資による一時的な損失を給与でカバーできるメリットもあります。
サラリーマンが実践すべき長期投資スタイル
では、具体的にサラリーマンがどのように長期投資を実践すればいいのか、いくつかのポイントをご紹介します。
「時間」が最大の味方になる理由を考えよう
長期投資の最大のメリットは「時間を味方につけられる」ことです。株式市場は、一時的に大きく下落することがあっても、長期的に見れば世界経済の成長とともに上昇してきました。
複利効果により、最初は小さな利益でも、それを再投資することで雪だるま式に資産が増えていく期待が持てます。
サラリーマンは働きながら定期的に投資資金を投入し、気がつけばまとまった金額に育っている、という理想的なパターンを狙いやすいのです。
短期的な予想の難しさを知ろう
相場の動きを短期で正確に予想できる人は、ほとんどいないと言われています。
プロの投資家ですら難しいのが、マーケットの短期的な動きです。
サラリーマンであれば、なおさらその予想は困難でしょう。
むしろ「短期的にどう動くかわからない」からこそ、長期的な視点でじっくり保有し、相場の乱高下を乗り越える姿勢が大切です。
何はともあれリスクを抑える分散投資が基本
どんなに優良な企業の株式でも、絶対に値下がりしないという保証はありません。
リスクを抑えるためには、複数の銘柄や資産クラス(国内外の株式、債券、不動産投資信託など)に分散して投資するのが鉄則です。
iDeCoやNISAの枠を利用する場合でも、商品を1本に絞るよりは、複数の投資信託などを組み合わせてリスクを低減する方法が一般的ですよね。
わたしの経験上、「株式100%で大丈夫!」という強気スタイルよりは、自分のリスク許容度に合わせて債券や現金ポジション、あるいはオルタナティブ資産などを取り入れたほうが、心の安定感が増すと感じています。
分散投資することで、一時的にどれかが値下がりしても、他の資産がカバーしてくれる効果が期待できます。
生活防衛資金と投資資金のバランスを取ろう
長期投資をするうえで大切なのは、「投資に回すべきお金」と「手元に残しておくべきお金」のバランスをしっかり考えることです。
急に車の修理や家電の買い替えが必要になったり、家族のイベントで大きな出費が必要になったりすることもありますよね。
そうしたときに投資を取り崩すことになってしまうと、長期投資の効果が半減してしまいます。
そのため、数カ月から半年分の生活費など、生活防衛資金は現金などで確保しておくと安心です。
わたしも、最低限の緊急資金は定期預金や普通預金で温存し、その上で余剰資金を投資に回すようにしています。
あらかじめ生活防衛資金があれば、相場の急落があっても「まぁ、投資分は長期で運用するつもりだから大丈夫」と落ち着いていられます。
必要な情報だけを選ぶ“情報ダイエット”
投資家にとってニュースや情報収集は大事ですが、過剰な情報はむしろ不安をあおり、焦ってしまう原因になります。特にネガティブなニュースは刺激が強いため、どうしても目につきやすいですよね。
わたしは、経済が不安定になった時ほど、意図的に資産チェックの頻度を減らすようにしています。
あまりにしょっちゅう見ると、売りたくなる誘惑に負けそうになるからです。
投資は長期勝負なので、「見ているだけで心が乱される情報」は、なるべく避けるのが吉です。
わたしは普段から、自分が信用している情報源(公式発表や経済指標など)を中心に、あとは投資方針に大きな影響がない場合はスルー、というスタンスを貫いています。
いわゆる“情報ダイエット”ですね。これもストレスを減らし、長期投資を続けるコツだと思います。
まとめ
今回は、「日米の株価が大幅に下落しそう」「米国景気が不安定かも」というニュースが飛び交うタイミングでも、焦らず長期投資を継続するための考え方をお伝えしました。
①相場の上下に不安を感じる理由
短期的な値動きにフォーカスしがちで、不安を増幅させる心理が働きやすい。
②短期投資と長期投資の違い
短期投資は大きく儲けるチャンスがある一方、相場のチェックや心理的負担も大きい。長期投資はコツコツ時間を味方につける安定感が魅力。
③サラリーマンが長期投資を選ぶメリット
安定収入があるため、継続的に投資できるうえ、本業の昇給やボーナスを活用できる。
④サラリーマンが実践すべき長期投資スタイル
「時間を味方にする」「短期予想の難しさを知る」「分散投資」「生活防衛資金を確保」「情報ダイエット」で余計な不安を減らす。
サラリーマンとして働きながらの投資は、正直なところ、「平日は仕事で忙しい」「家族サービスもある」などの制約が多いですよね。
わたし自身も、相場が荒れたときに冷静でいるのは難しいと感じることがあります。
だからこそ、短期的な値動きに一喜一憂するのではなく、長期的に「どうなってほしいか」をイメージしながら、焦らず投資を続けるのが得策だと考えています。
景気の先行きがどうであれ、世の中は常に変化していきます。
大事なのは、その変化に振り回されすぎず、「長期的な成長を期待する投資スタイル」を貫くことだと思います。
そして、必要なときには柔軟に軌道修正しながら、まずは自分自身の収入アップやスキルアップを図ることが、サラリーマンにとっての最強の資産形成術ではないでしょうか。
ぜひ今回の記事を参考に、不安定な相場でも長期投資をブレずに続けられるよう、投資スタイルを見直してみてくださいね。

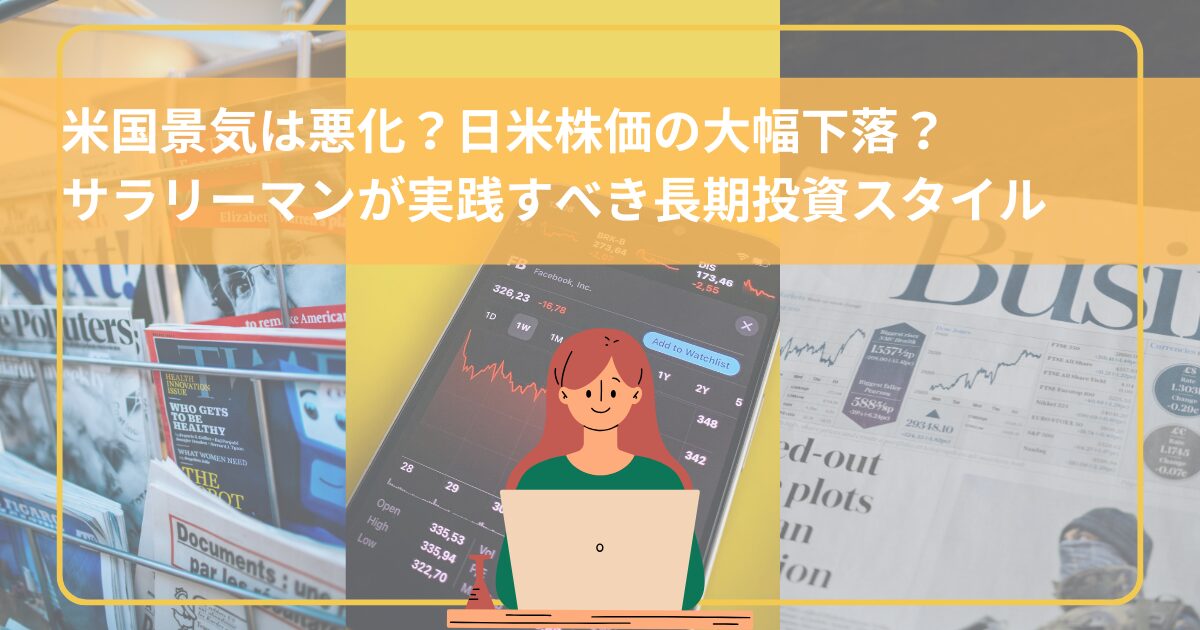
コメント